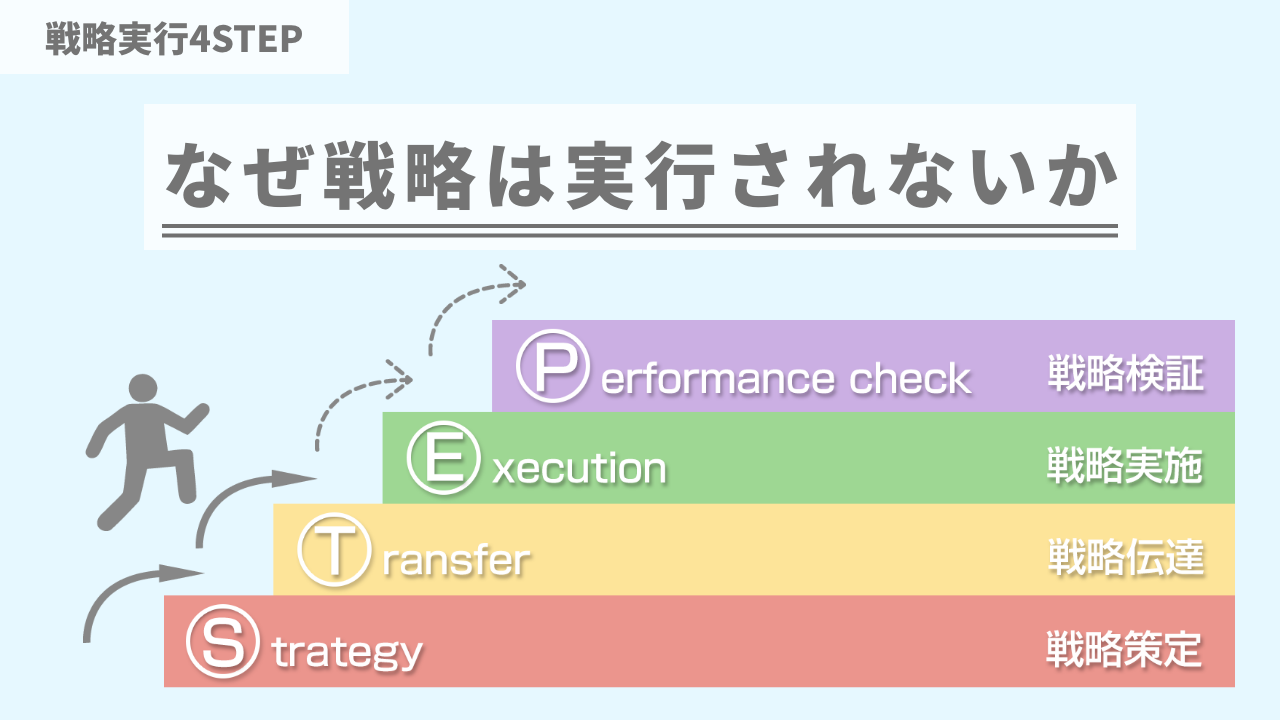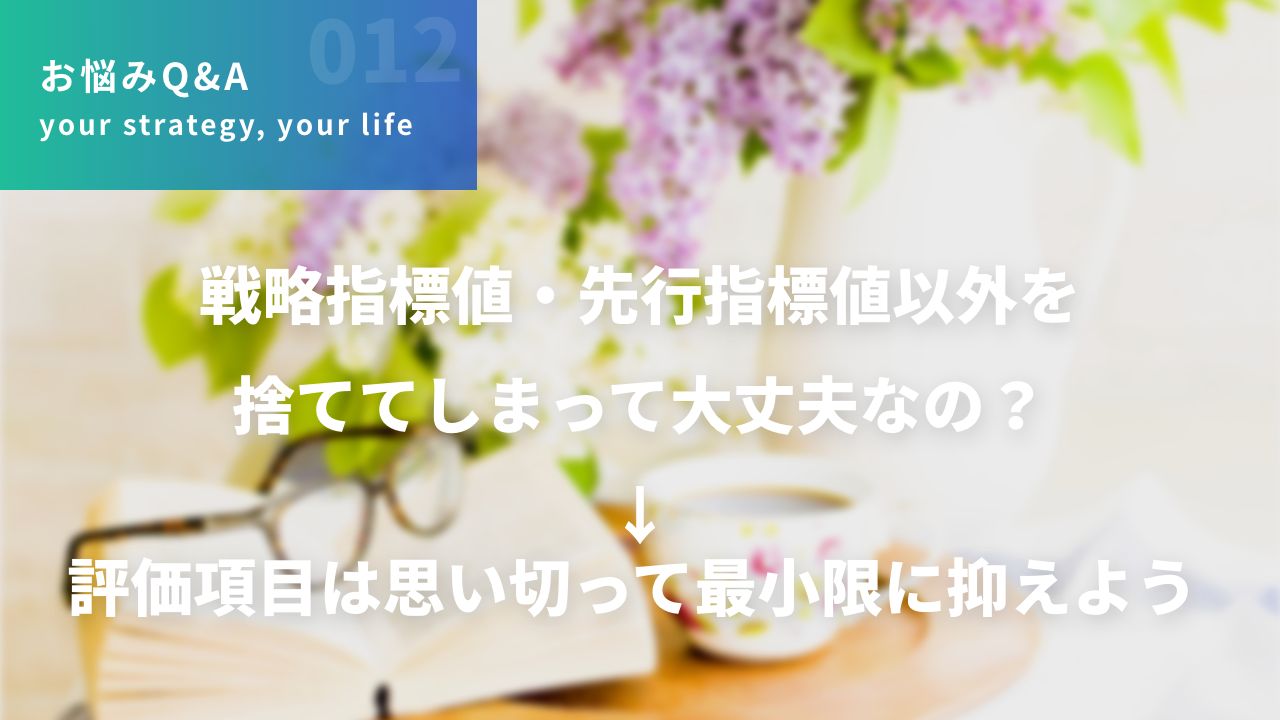【第3話】みのり 電子書籍プロジェクトに抜擢される

K書店からの帰り道、久保とみのりは地下鉄に乗った。超時空社のオフィスは、地下鉄やJR・私鉄のターミナル駅から、私鉄に少々乗った駅から、7分ほど歩いたところにある。アクセスがよいとは到底言えない。
地下鉄の中で、久保は車内を見回して言った。
「みんな、スマホ見てるな。」
シートに腰掛ける人、つり革につかまっている人、ホームで電車を待つ人。かなりの人が一様にスマホなどの液晶画面を見ている。
久保:こんなに人がいて、みんなそれぞれ同じことしているなんて、なんか気味が悪いな。
みのり:本を読まなくなっているっていうけど、なんだかんだ活字は読んでいますよね。
久保: あくまで本離れで、活字離れじゃないってことか。
みのり:メールやSNSとか、書くほうも結構してますし。
久保:店長が、うちでは電子書籍を出さないのかって聞いてきたんだが、 これだけSNSが広まって誰もが簡単に発信できるようになると、そもそも、誰も本を読まない時代になるのかもな。
みのり:でも、出版社のものには、ちゃんと編集という技術に裏打ちされた作品が……。
久保:お前に言われても全然説得力がないよ。それより、お前、仕事やる気全然ないだろ。
みのり:そんなことないですよ。
久保:さっきだって、電話ばかりしてたじゃないか。
みのり:……
久保:返す言葉もないか。そんなんだから、みんなに都合のいいように半端な仕事頼まれちゃうんだぞ。お前につまらないもの作らせるよりは、その方が会社のためになるもんな。
みのり:ひどい……。
久保:やる気がないなら、さっさと寿退社でも、転職でもしたらいい。その方が、幸せじゃないのか。本気で編集の仕事したら、編集長みたいに残業ばかりになるんだ。ワークライフバランスとか、育児と仕事の両立とか、無理だろ。
みのりは悔しくて黙り込んだ。
この業界ではワークライフバランスとか言っていられない現状があるのは事実だ。
だけど、もし人間が、皇帝ペンギンのように「男性が子育てをする」生物だったら、社会の制度なんてとっくの昔に変わっていたんじゃないかという気がする。
皇帝ペンギンは、オスが卵を孵化させて、メスが交替してくれるまで、飲まず食わずでヒナを守るイクメン動物の代表なのだ。みのりの頭のなかで、擬人化された皇帝ペンギンたちが動き出す。
ペンギンブックスは、南極に本社を構える従業員100人(羽)の会社で、20代から30代の男性ペンギンが30羽働いている。そのうち10羽が卵を温めていて、20羽は孵化したばかりの雛を抱えている。
「課長、実は卵が不安定なんでペン」
「それはいかんな、しばらく休憩室に行きなさいペン。」
「ピンキーさん、Y社から電話だペン」
「あ、ピンキーさんなら今ベビールームでエサやり中だから、折り返し電話するように伝えてペン」
「どうしたペン、顔色が悪いペン?」
「う、生まれるペン。予定日より早いペン」
「救急車だペン!」
皇帝ペンギンのオスは、卵を産んでから餌を食べに行ったメスが戻ると、餌を食べに駆け出す。中にはえさ場にたどり着く前に衰弱して命を落とすペンギンもいるそうだ。
子孫を残すというのは命がけなのだ。
「実は、妻が戻るのが遅れているペン」
「そうか、ならば育児勤務の延長を申請しておきなさいペン」
人事ペンギン大変だな、こりゃ。ぷぷぷ。
「おい、秋山!」
みのりは、急に現実に引き戻された。
「お前、おれの話聞いていたのか?」
「あっ、久保さん。どうかしましたか?」
久保が呆れた顔をして、みのりを見たとき、ちょうど地下鉄は、ターミナル駅に到着した。みのりは、慌てて、降りる支度をする。
久保:うん? 降りるのか?
このターミナル駅で、地下鉄は私鉄に乗り入れており、超時空社に行くには、このまま乗って行けばよい。
みのり:あっ、すみません。今日は、私は直帰の予定なので、ここで降ります。
久保:今日は。っておまえいつも直帰じゃないか。
みのり:そんなことないですって。編集長には直帰の電話をしてあります。
久保:勝手にしろ。
地下鉄を降りたあと、みのりはファイナンシャルプランナー資格取得のためのスクールに向かいながら、先ほど久保に言われたことについて考え込んでいた。
仕事に注力できていないのは、自分自身がよくわかっていた。
でも、入社してから4年間、人が足りないという理由で、雑用や誰かの手伝いばかりで、全然仕事を任せてくれない会社が悪いんだ。
大手出版社であれば、こんなことはないはずなのに。久保さんに言われるまでもなく、さっさと転職させてもらいます。そのためには、資格も必要よね。
などと考えながら、また熱心にスマホの求人広告をチェックしはじめた。
**********
翌日出社すると、みのりは編集長に呼ばれた。
編集長:電子書籍つくれ
みのり:はっ?
編集長:とにかく、野中さんと一緒に社長のところに行ってこい。
みのり:えっ、社長のところですか?
編集者でありながら、実は電子書籍についてよくわかっていない。私がわかっていないことは編集長もわかってるはずなのに、嫌がらせかしら。もしかして、仕事のふりしてスクールに通っているのがばれたかな。
みのりは木村編集長の目を見た。
木村編集長の目は細いので、表情がわかりにくい。いつも、眠っているのかと思ってしまう。
「ま、いいや。社長に直接聞いてみよう。」
みのりは野中とともに社長室に向かった。社長室といっても部屋ではなくパーテーションの向こうというだけだ。吉川社長は、会社として電子書籍に取り組むこと、まずはトライアル的な電子書籍を作りたいこと、それを二人に任せたいことを伝えた。
野中:あの、私、電子書籍に関しては全くの素人なんですが。
みのり:あっ、私も、触ったことありません。
「幹部も誰も触ったことがないそうだ。君たち二人が適任だと私は思っている。まずは、これを使っていろいろ調査してみてくれ。」
と言って、社長は、二種類の電子書籍端末を二人に渡した。 自席に戻ったみのりは、仕事が増えたらスクールに行けなくなるかもしれないと思いつつも、はじめて仕事を任せてもらえたことをうれしく思い、電子書籍端末の電源を入れた。
つづく
はじめから読む

ユアスト 江村さん
第1話は下記より御覧ください。
【第1話】超時空社